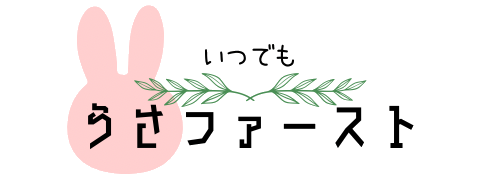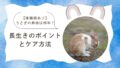野生とペットのうさぎって、何が違うの?

実は、まったく別の種類なんです!
「うさぎ」と一口に言っても、ペットと野生では大きな違いがあります。
では、その違いはなんでしょうか?
ペットのうさぎはカイウサギ、そして野生のウサギはノウサギという種類です。
この記事では、ペットと野生のうさぎの特徴を詳しく比較していきます。
彼らがどのように進化し、環境に適応してきたのか…
もしかしたら、意外な違いに驚くかもしれません!
ペットのうさぎ=カイウサギとは?

ペットとして飼われているうさぎはカイウサギ(飼いウサギ)と呼ばれます。
カイウサギの祖先はアナウサギという種類のうさぎで、もともとはヨーロッパを中心に生息していました。
この章では、「カイウサギとは何か?」について、詳しく解説していきます!
ペットうさぎの祖先は「アナウサギ」
アナウサギは野生のノウサギとは異なり、地面に穴を掘って暮らす習性を持つうさぎです。
彼らは群れを作り、地下にワーレンと呼ばれる巣穴を作って生活します。
この群れを作る習性と定住する習性があったため、人間による管理がしやすく、家畜化が進みました。
さらに、アナウサギは繁殖力が高く、短期間で多くの子を産みます。
そのため、食用や毛皮用、愛玩動物としての飼育に適していたのです。
こうして人間と共に暮らすようになったアナウサギ。
彼らは長い歴史を経て、現在のペットのうさぎ(カイウサギ)へと進化を遂げていきました。
品種改良されてきたカイウサギ
アナウサギが初めて人に飼われたのは、およそ2000年前といわれています。
人間の手によって繁殖が管理され、さまざまな特徴を持つうさぎが誕生しました。
カイウサギは、長い歴史の中で品種改良を重ねられてきたのです。
現在、ペットとして人気のうさぎには様々な品種があります。
例えば、丸い小さな体のネザーランドドワーフや、耳の垂れたホーランドロップなど。
この他にも、たくさんの品種がいるのがカイウサギの特徴です。
また、ARBA(アメリカのうさぎのブリーダー協会)に登録される品種は、年々増加しています。

垂れ耳に立ち耳…どちらも可愛いね

当然よ

比べられるものじゃないでし
アナウサギとノウサギは別の種類
ここで注意したいのは、「アナウサギ」と「ノウサギ」はまったく別の種類であるということです。
- アナウサギ(ペットうさぎの祖先)
巣穴を掘る習性があり、群れで生活する。
- ノウサギ(日本の野生種)
巣穴を掘らず、単独行動が基本。
日本に生息している野生のうさぎは「ノウサギ」です。
ノウサギは、ペットのカイウサギとはまったく異なる進化を遂げた動物です。
そもそも種類が違うので、体の形や習性から、異なる性質を持っています。
日本に住む野生のうさぎの種類

日本にはペットのうさぎ(カイウサギ)とは異なる、野生のうさぎが生息しています。
彼らは厳しい自然環境に適応し、それぞれの地域に合った進化を遂げてきました。
ここでは、日本に住む代表的な野生のうさぎを紹介します。
日本にいる代表的な野生うさぎ
以下は、日本に生息する代表的な野生のうさぎです。
- ニホンノウサギ(本州・四国・九州)
日本で最も広く分布しているうさぎです。
夏毛は茶褐色で、冬毛は地域によって白くなることがあります。
俊敏な動きが特徴で、危険を察知すると素早く逃げる能力を持っています。
- エゾユキウサギ(北海道)
北海道に生息するうさぎです。
寒冷地に適応するために、冬毛は真っ白になります。
夏は茶色の毛に変わるため、季節ごとに体の色が変わるのが特徴です。
- エゾナキウサギ(北海道の高山地帯)
うさぎの仲間ですが、耳が小さく、ずんぐりとした体型をしています。
寒冷地に適応し、特に山岳地帯の岩場に多く見られます。
草食性ですが、岩場に生える植物や苔などを食べます。
- アマミノクロウサギ(奄美大島・徳之島)
絶滅危惧種として指定されている、貴重なうさぎです。
黒っぽい体毛と短い耳が特徴。
奄美大島と徳之島にのみ分布し、主に森林に生息しています。
このように、日本にはさまざまな種類の野生のうさぎが存在しています。
そして、それぞれが地域の環境に適応しながら生きています。
ペットのうさぎとは異なり、人間の手が加えられていないため、本来の野生の姿を残しているのが特徴です。
野生のノウサギの生態は?
日本に生息する野生のノウサギ。
彼らは、厳しい自然環境の中で生き抜くために独自の習性を持っています。
この章では、ノウサギの特徴とアナウサギとの違いについて詳しく解説します。
ノウサギは単独行動が基本
ペットのうさぎの祖先であるアナウサギは、巣穴を掘り集団で生活する習性があります。
しかし、ノウサギは基本的に単独行動を好み、群れを作ることはありません。
繁殖期以外は他のうさぎと接することがほとんどなく、広い行動範囲を持ちながら生活しています。
巣穴を掘らず、草むらや林で生活
アナウサギとは違い、ノウサギは地面に穴を掘ることはありません。
代わりに、草むらや茂みの中でじっと身を潜め、外敵から身を守ります。
天敵に襲われそうになった場合は、一気に長距離を走って逃げる能力を持っています。
野草や樹皮を食べる
ノウサギの主な食べ物は、野草や木の葉、樹皮、木の芽などです。
厳しい環境の中でも生き延びるため、硬い樹皮なども食べる適応力を持っています。
一方、アナウサギは比較的柔らかい草や葉を好み、野生では牧草や低木の若葉などを食べます。
このように、ノウサギは厳しい環境の中でもたくましく生き抜いています。
ペットのうさぎと野生のうさぎの違い

ペットのうさぎ(カイウサギ)と、野生のうさぎ(ノウサギ)。
同じ「うさぎ」という名前でも、体のつくりや特徴が大きく異なります。
これは、ペットのうさぎが長い時間をかけて人間に飼いやすいように改良されてきたのに対し、野生のうさぎは自然界で生き抜くための進化を遂げてきたためです。
見た目の特徴の違い
ペットのうさぎと野生のうさぎでは、体型や体の特徴にも明確な違いがあります。
| 項目 | ペットのうさぎ(カイウサギ) | 野生のうさぎ(ノウサギ) |
|---|---|---|
| 体型 | 丸みを帯びた体型 | スリムで筋肉質 |
| 体重 | 1〜2.5kg(小型種)〜6kg(大型種) | 2〜5kg(地域による) |
| 耳の形 | 品種によって異なる(立ち耳・垂れ耳) | 立ち耳が基本 |
| 毛の色 | 品種ごとにさまざま(白・黒・茶・グレーなど) | 季節によって変化(冬に白くなる種も) |
体型・体格の違い
ペットのうさぎは、基本的にふっくらとした丸みのある体型をしています。
特に、ネザーランドドワーフやホーランドロップなどの小型品種は、コンパクトな体型と丸い顔が特徴です。
一方、野生のうさぎはスリムで足が長く、俊敏に走るための筋肉が発達しています。
敵から素早く逃げる必要があるため、無駄な脂肪が少なく、全体的に引き締まった体つきをしています。
耳の形や大きさの違い
ペットのうさぎの耳は品種によってさまざまです。
しかし、特にロップイヤーと呼ばれる垂れ耳の品種は、ペットならではの特徴です。
一方で、野生のうさぎの耳はすべて立ち耳。
周囲の音を素早く察知できるように、発達しています。
毛色の違い
ペットのうさぎは、人間が見た目の可愛さを重視して改良したため、毛色のバリエーションが豊富です。
白、黒、茶色、グレーなど、さまざまなカラーが存在します。
一方、野生のうさぎの毛色は、環境に適応するために進化しており、保護色となるような茶色や灰色が基本です。
特にエゾユキウサギのように冬に白く変化する種もおり、雪の中で外敵に見つかりにくくなっています。
習性・暮らし方の違い
ペットのうさぎと野生のうさぎでは、暮らし方や行動パターンに大きな違いがあります。
これは、ペットのうさぎが人間に飼われるように進化したのに対し、野生のうさぎは厳しい自然環境の中で生き抜くための習性を持っているからです。
| 項目 | ペットのうさぎ(カイウサギ) | 野生のうさぎ(ノウサギ) |
|---|---|---|
| 生活スタイル | 群れ(アナウサギ由来) | 基本的に単独行動 |
| 巣作り | ケージや部屋の隅を好む | 草むらや林に身を潜める |
| 活動時間 | 朝・夕方に活発(薄明薄暮性) | 早朝・夕方に活動(薄明薄暮性) |
| 逃げるときの動き | 物陰に隠れる | 俊足で長距離を走る |
ペットのうさぎは「群れ」、野生のうさぎは「単独行動」
ペットのうさぎの祖先であるアナウサギは、地面に巣穴を掘り、群れで生活する習性があります。
そのため、カイウサギも本能的に仲間を求める傾向があり、人懐っこい個体も多いです。
一方、ノウサギは単独行動が基本。
広範囲を移動しながら暮らすため、縄張り意識が強く、他のうさぎとあまり関わりません。
ペットは「安心できる場所」、野生は「隠れる場所」
ペットのうさぎはケージの中や部屋の隅など、安心できる場所を巣のように使います。
中には、布やおもちゃを集めて巣作りをする個体もいます。
野生のうさぎは、巣穴を掘らずに草むらや林の中に身を潜めるのが特徴です。
敵から見つかりにくい場所を選び、じっと息を潜めて過ごします。
活動時間はどちらも「薄明薄暮性」
ペットのうさぎも野生のうさぎも、「薄明薄暮性(はくめいはくぼせい)」です。
薄明薄暮性とは、主に朝と夕方に活発に動く生活リズムのことです。
これは、天敵である肉食動物が活動しにくい時間帯に動くことで、生存率を上げるための習性です。
逃げるときにペットは隠れる、野生は走る
ペットのうさぎは、驚いたときに物陰に隠れることが多いです。
ケージの隅や家具の後ろに身を潜めて、外敵から身を守ろうとします。
一方、野生のうさぎは驚くと一気に走り出し、長距離を猛スピードで逃げるのが特徴です。
特にノウサギは後ろ足の筋肉が発達しており、時速60km近くで走れる種類もいます。
このように、ペットのうさぎと野生のうさぎでは、環境によって習性や行動が大きく異なります。
繁殖の違い
ペットのうさぎと野生のうさぎでは、繁殖の仕方や生存率にも大きな違いがあります。
これは、環境の違いだけでなく、長年の進化や人間による改良の影響も関係しています。
ペットのうさぎ:人間の管理下で安全に繁殖
ペットのうさぎ(カイウサギ)は、人間が管理しやすいように改良されてきました。
そのため、性格が温和で繁殖しやすい個体が選ばれてきたという特徴があります。
- 一般的に生後4〜6か月で繁殖可能になる
- 1回の出産で平均7匹ほどの子うさぎを産む
- 人間の管理下で育つため、生存率が高い
ペットのうさぎも短期間で繁殖を繰り返してしまうため、飼い主が適切にコントロールすることが大切です。
野生のうさぎ:多産だが生存率が低い
一方、野生のうさぎは外敵が多く、自然界で生き残るのが厳しいです。
そのため、とにかく数を増やして種を存続させる戦略をとっています。
- 1年に数回の出産を行う
- 年間で約10匹の幼獣を産むことが可能
- 子うさぎの生存率は低く、多くが捕食される
特にノウサギは、天敵が多いため、短期間で繁殖しながら数を増やすことが必要です。
しかし、生き残れる個体は限られており、厳しい自然環境の中でたくましく成長していきます。
このように、ペットのうさぎと野生のうさぎでは、繁殖に関する戦略が大きく異なります。
ペットのうさぎは安全な環境で長生きできる一方、野生のうさぎは多くの子を産みながら、厳しい環境の中で生き残るために適応しているのです。
野生のうさぎを見つけた時の注意点

森や山道で野生のうさぎを見つけることがあるかもしれません。
特に春や夏は子うさぎを目にする機会が増えます。
しかし、かわいいからといってむやみに近づいたり、保護しようとしたりするのはNGです。
ここでは、その理由について詳しく解説します。
触らない・保護しない方がいい理由
野生のうさぎを見つけたとき、「助けてあげたほうがいいのでは?」と思うこともあるかもしれません。
実際に、筆者も山でノウサギを見かけた際、気になって近づきたくなってしまったことがあります。
しかし、基本的にはそっとしておくのが正解です。
その理由を見ていきましょう。
法律で野生動物の捕獲は規制されている(鳥獣保護法)
日本では鳥獣保護管理法(鳥獣保護法)により、野生動物の無許可での捕獲や飼育が規制されています。
違反した場合、罰則が科される可能性があります。
そのため、保護目的であっても勝手に連れて帰ることは推奨されません。
詳しくは、お住まいの自治体や環境省の公式情報をご確認ください。
赤ちゃんのノウサギには親がいる(巣から離れても世話されている)
野生のノウサギの赤ちゃんは、巣の外にいることがよくあります。
これは親うさぎが外敵に気づかれないように、あえて巣を離れる習性があるからです。
「親がいない=迷子」ではないため、むやみに連れて行くと逆に親子を引き離してしまうことになります。
もし子うさぎを見つけても、近くに親が戻ってくる可能性が高いので、そのままにしておきましょう。
感染症のリスクがある(ダニやノミが媒介)
野生のうさぎには、ノミやダニ、寄生虫などが付着していることが多いです。
また、それらを媒介して人に影響を与える可能性があります。
特に傷口や粘膜に触れると、病原体が侵入し、健康に悪影響を及ぼすことも考えられます。
感染症のリスクを避けるためにも、野生のうさぎにはむやみに触れず、距離を保つことが大切です。
直接触れたり、傷口から菌が入ったりすると、感染するリスクが高まります。
野生のうさぎを見つけても、触らない・近づかないのが安全です。
野生のうさぎはそっとしておくのがベスト
野生のうさぎを見つけると、つい助けたくなってしまいますよね。
しかし多くの場合、人間が手を出さないほうがうさぎにとって最良の選択です。
- 法律で保護されているため、捕獲や飼育は避ける
- 赤ちゃんうさぎには親がいるので、勝手に保護しない
- 感染症リスクがあるため、触らない・近づかない
野生のうさぎは、厳しい自然の中でたくましく生きています。
見つけたら静かに観察し、そのままそっとしておいてあげましょう。
ペットのうさぎにも残る本能は?

ペットのうさぎ(カイウサギ)は、長い時間をかけて家畜化されてきました。
しかし、今でも野生の本能を持ち続けています。
驚いたときに急に走り出したり、暗い場所に隠れたがったり…
そうした反応も、本能によるものが多いです。
うさぎが安心して暮らせるようにするためには、これらの本能を理解し、適した環境を整えることが大切です。
「なんでこんな行動をするの?」と思ったときは、うさぎの本能を思い出してみましょう。
すぐに隠れたがる
うさぎは元々、天敵に狙われやすい動物。
そのため、とても警戒心が強いです。
知らない音や突然の動きに驚き、物陰に隠れようとすることがあります。
筆者のうさぎも、聞き慣れない音や知らない人の気配がすると、慌ててケージに逃げ込みます。
野生のアナウサギが物陰に隠れるのと、同じようなものなのかもしれません。
なるべく、うさぎにストレスをかけないよう注意することが重要です。
- トンネルを使用したりケージに布をかけて隠れ場所を作る
- 急に抱っこせず安心できる環境で少しずつ慣れさせる
- 大きな音や急な動きで驚かせないように気を付ける
走ったりジャンプしたりする
うさぎはいつでも素早く逃げられるように、突然ダッシュしたり、ジャンプしたりすることがあります。
これは「逃げるための準備」としての本能的な行動です。
ただし、ペットのうさぎの場合、喜びや興奮を表していることもあります。
これは、ケージから出してもらえた瞬間などに、「自由だ!」と体を使って楽しんでいるのです。
筆者のうさぎも、特に若い頃は、飛んだり跳ねたりと大忙しでした。
走り回ったあとに「どう?今の見てた?」と飼い主の様子をうかがう姿も可愛いポイントです。
- 狭いケージの中だけでなく、部屋の中で自由に動ける時間(部屋んぽ)を作る
- 足腰に負担がかからないよう、滑らない床を用意する
- 驚かせてパニックにならないよう、優しく接する

うーちゃんはいつもドヤ顔で走り回ってたよね

私の華麗な身のこなしを見せてあげてるのよ
部屋んぽについて、詳しくは以下の記事も参考にしてください。
なんでもかじろうとする
うさぎの歯は、一生伸び続けます。
そのため、硬いものをかじって歯を削る習性があります。
この本能があるため、放っておくと家具やコードをかじることも。
筆者の場合、コードだけでなく革製品などもよくかじられました。
ブランドバッグなどが標的にされやすく、それらは何度もボロボロにされています…
かじること自体をやめさせるのは難しいので、うさぎの周りに物は置かないようにしてください。
- チモシー(牧草)を主食にし、常に食べられるようにする
- かじっても安全な木のおもちゃやわらマットなどを用意する
- コード類は100均などにある専用カバーをつけて対策する
土を掘ろうとする
うさぎは元々、穴を掘って暮らしていました。
そのため、今でも前足で床を引っかいたり、マットを掘るような動作をすることがあります。
筆者のうさぎも、飼育スペースのマットをよくホリホリしています。
我が家の場合、何か嫌なことがあってイライラしているときなどにこの行動を見せます。
きっと、マットをホリホリして気持ちを落ち着かせようとしているのでしょう。
- 毛布やマットを敷いて、掘る遊びができる環境を作る
- カーペットを傷つけないよう、うさぎ専用の掘り遊び用マットを活用する
- 叱るのではなく、「掘っていい場所」を用意する

ホリホリはふーちゃんがよくしてます

ホリホリ上手でし♫
夜や朝に活発になる
うさぎは、夜明けや夕方に活発に動く薄明薄暮性(はくめいはくぼせい)の動物です。
昼間は寝ていることが多く、夜や朝に遊びたがるのは本能的なものです。
よく聞くのが、夜寝る前にうさぎをケージに入れると、柵をかじってうるさいという話。
夜はうさぎにとって活発な時間。
遊び足りなければ、「もっと遊ばせてよ!」と猛アピール!
うさぎは結構頑固なので、なにがなんでも自分の意思を貫き通そうとします。
この「ケージガジガジ攻撃」で、私もよく寝不足になったものです。
- 夜にうるさくならないよう、日中にしっかり遊ばせる
- 夜中にケージをガタガタさせる場合は、広めのサークルを用意しておく
- うさぎの生活リズムを尊重し、無理に昼間に遊ばせようとしない
まとめ

野生のうさぎとペットのうさぎは別の種類
うさぎはペットと野生ではそもそも異なる種類であり、生態や習性にも大きな違いがあります。
ペットのうさぎは人に慣れやすく、比較的温和な性格です。
野生のうさぎは本能的に警戒心が強く、群れで行動することが多いのが特徴です。
また、ペットのうさぎは穴を掘る習性が薄い一方で、野生のうさぎは巣穴を掘って身を守りながら生活します。
見た目が似ていても、野生のうさぎをペットとして飼うことはできません。
ペットのうさぎには適切な飼育環境を整え、野生のうさぎとは適切な距離を保つ。
それぞれの生態を理解した上で接していくことが大切です。