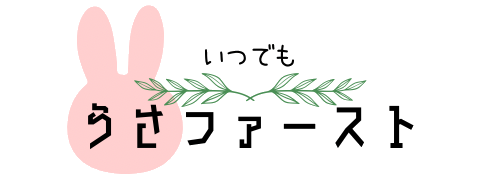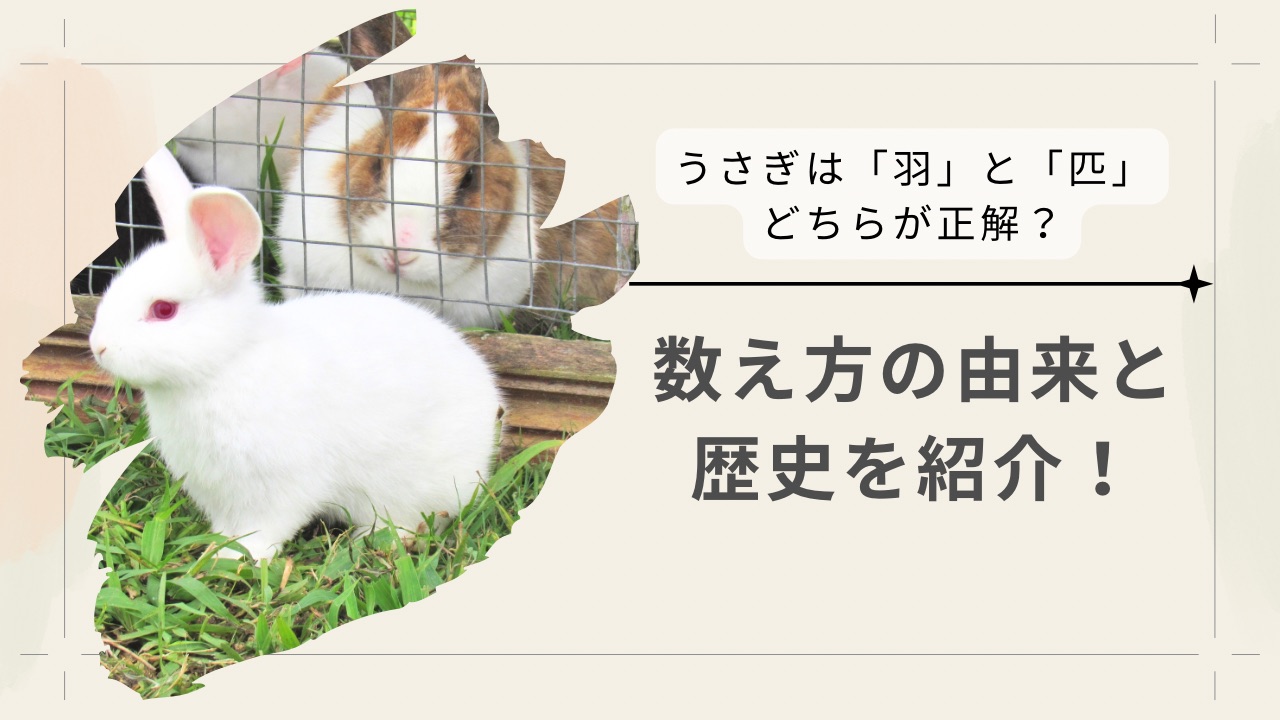「うさぎの数え方は“一羽”?それとも“一匹”?」

実は、どちらも正解なんです
うさぎの数え方といえば「一羽、二羽」?それとも「一匹、二匹」?
実はどちらも正しく、状況によって使い分けられているんです。
でも、なぜ鳥でもないのに「羽」と数えるのでしょうか?
そこには歴史的な背景や文化的な理由がありました。
さらに、あまり知られていない「耳」や「兎」という数え方も存在するんです!
たくさんあるうさぎの数え方、その由来は?
うさぎ好きならぜひ知っておきたい、奥深い日本語の世界を一緒に探ってみましょう!
うさぎの数え方は「匹」だけじゃない?

「うさぎの数え方」と聞いて、「一匹、二匹」と数えることを思い浮かべる人も多いかもしれません。
また、一羽、二羽と数える方法も有名ですよね。
結論から言うと、どちらの数え方も間違いではありません。
実はうさぎの数え方には複数のバリエーションが存在します。
なかには、あまり聞き慣れない「耳」や「兎」といった珍しい数え方もあるのです。
では、それぞれの数え方がどのような場面で使われるのか、詳しく見ていきましょう!
うさぎの数え方と由来の一覧表
うさぎには複数の数え方があり、それぞれ異なる背景があります。
以下にまとめてみました!
| 数え方 | 読み方 | 用途・特徴 |
|---|---|---|
| 羽 | わ | 伝統的な数え方。歴史的背景から「鳥」として扱われたため。 |
| 匹 | ひき | 現代では最も一般的。小型動物に使われる単位。 |
| 耳 | みみ | 江戸時代の文献においても記録されている。うさぎの耳に着目した数え方。 |
| 兎 | と | ことわざなどに登場する独特な数え方。現在ではほぼ使われない。 |
現代では「匹」と「羽」が主流
現在、日常生活でうさぎの数え方としてよく使われるのは「匹」と「羽」です。
特に現代では、「匹」の方が一般的です。
- 「匹」
犬や猫などの小動物と同じ分類で数える方法。
ペットとして飼われるうさぎに対して一般的に使われます。
- 「羽」
昔からの伝統的な数え方。
文化や歴史を感じさせる表現です。
ペットショップや飼育書では「匹」が多く、文学作品や昔の文献では「羽」が使われることがあります。
どちらも正しいので、状況に応じて使い分けると良いかもしれません。
「兎」や「耳」という珍しい数え方も
「耳」や「兎」という数え方は、あまり馴染みがないかもしれません。
しかし、かつて古い文献などで使われていたという記録が残っています。
- 「耳」
うさぎの長い耳に由来する数え方。
「一耳、二耳」という表現があったとされていますが、現在ではほぼ使われません。
- 「兎」
古い書物の中に見られる数え方。
「一兎、二兎」という形で使われていましたが、現在の日本語では一般的ではありません。
このように、うさぎの数え方は時代や文化によって変化しており、さまざまな背景を持っているのです。
次の章では、「なぜうさぎを“羽”で数えるのか?」について、歴史的な由来を詳しく解説します!
うさぎを「羽」で数える由来は?

うさぎは鳥ではないのに、なぜ「一羽、二羽」と数えられるのでしょうか?
実は、この数え方にはいくつかの説があり、宗教的な背景や文化の影響を受けていると考えられています。
ここでは、代表的な6つの説を紹介しながら、なぜ「羽」が使われるようになったのかを紐解いていきます。
説①「僧侶のこじつけ」説
この説は、江戸時代に徳川綱吉が発令した「生類憐みの令」が関係しています。
これにより、4本足の動物を食べることが禁止されていました。
しかし、僧侶たちはうさぎを「鳥」とみなすことで、食べることを正当化しようとしたのです。
- 2本足で立つ姿や、長い耳を鳥の羽に見立てた
- うさぎは鳥と似ているから大丈夫という解釈が生まれた
- そこで「羽」を使って鳥と同じ扱いにした
特に、日本では肉食禁止の時代にどうしても肉を食べたかった僧侶たちが、うさぎを鳥として扱うこじつけを考えたという話が伝わっています。
これはあくまで俗説ですが、「うさぎ=鳥」という発想が数え方に影響を与えた可能性は十分にあります。

とんだ僧侶たちですね
説②「名前の由来」説
うさぎの名前自体に、「鳥」を連想させる要素があるという説です。
- 「うさぎ」は 「鵜(う)」と「鷺(さぎ)」 が合わさった言葉ではないかと言われる
- 「鵜鷺(うさぎ)」→ 鳥と関連がある → 「羽」で数えるようになった
このため、猟師たちが鳥の仲間として捉えるようになったという説です。
言葉の成り立ちが数え方に影響を与えたと考えれば、この説も筋が通っていますね。

確かに鳥の名前が入ってるもんね
説③「捕獲方法」説
昔、うさぎは網を使って捕まえることが多かったそうです。
そのため、鳥と同じ「羽」で数えられるようになったのではないかという説です。
- 鳥を捕まえるときに使われる「網猟(あみりょう)」
- うさぎも網を使って捕らえられていた
- そのため、「鳥と同じように網で捕まえる → 数え方も羽に」
漁業と狩猟の文化が発展していた日本では、捕獲方法がそのまま数え方に影響を与えた可能性もあるのかもしれません。

どうしても鳥にしたかったのね
説④「耳の形状」説
うさぎの長い耳が鳥の羽に似ていることから、「羽」で数えられるようになったという説です。
- うさぎの耳は、ピンと立つと羽のように見える
- 束を意味する「把(わ)」と「羽(わ)」が同じ音
- 「耳を束ねる」ことから「一把(いちわ)」と呼ばれるようになった
この説は、うさぎを捕まえたときに長い耳を束ねて持ち運んだためではないかと言われています。

耳の形までこじつけるんかい
説⑤「文化的な視点」説
うさぎは日本の神話や伝承の中で神聖な動物とされていました。
- 月のうさぎ伝説や因幡の白兎(いなばのしろうさぎ)など、神話に登場する
- 他の動物と違う特別な数え方が与えられた可能性
特定の動物に対して独自の数え方をすることは、日本語の特徴のひとつです。
そのため、うさぎが神聖視される中で「羽」という独特の数え方が定着したのかもしれません。

うさぎは神聖なイメージ、ある
説⑥「味が鳥に似ている」説
少し意外かもしれませんが、うさぎの肉が鳥の肉に似ていたという説もあります。
- 日本では鳥肉は食べても良いが、獣肉は避ける風習があった
- そのため、「鳥の一種」という扱いにされた
肉の特徴が数え方に影響を与えた可能性も考えられますね。

説①と通じるものがありますよね
結局どの説が正しいの?
これらの説のうち、どれが本当に正しいかははっきりしていません。
いくつかの要因が組み合わさって「羽」という数え方が定着したと考えられます。
- 僧侶のこじつけ説
生類憐みの令が関係していたため。
- 名前の由来説
名前が鳥に関連していたため。
- 捕獲方法説
捕獲方法が鳥と同じだったため。
- 耳の形状説
耳の見た目が鳥の羽に似ていたため。
- 文化的視点説
神聖な動物だったため。
- 肉の味説
うさぎの肉の味が鳥に似ていたため。
現代では「匹」で数えられることが一般的になっています。
しかし「羽」という数え方も、歴史や文化の中で生まれた日本語の特徴的な表現なのです。
次の章では、「匹」と「羽」の実際の使い分けについて詳しく解説します!
なぜ今も「羽」という数え方が残っているの?
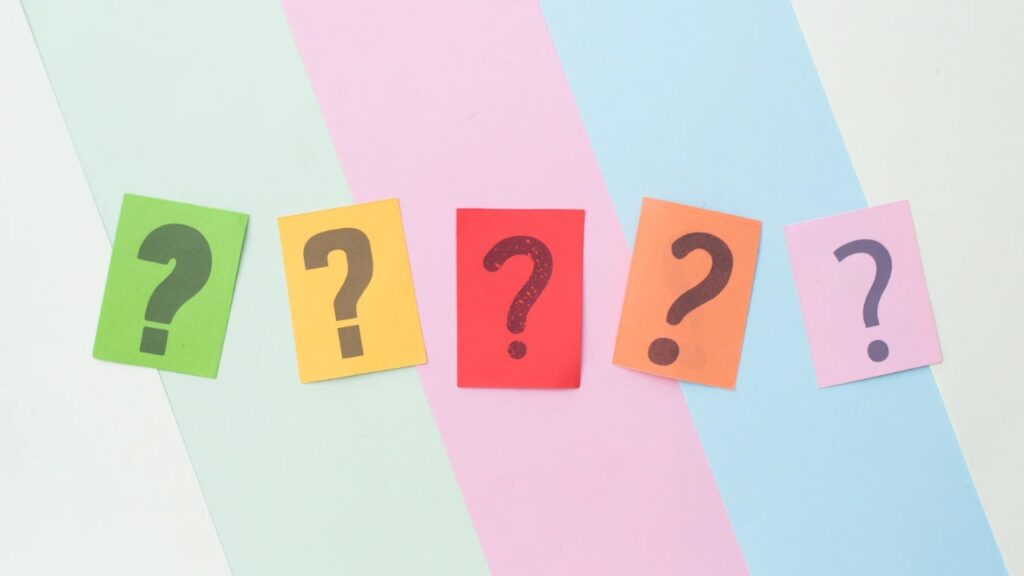
現在では「匹」が一般的ですが、「羽」という表現が完全になくなったわけではありません。
うさぎを一羽、二羽と数えるのを聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
では、なぜ「羽」は今も使われ続けているのでしょうか?
その理由を文化的・伝統的な視点から解説します。
日本語の伝統的な表現としての「羽」
「羽」という数え方は、単なる言葉の名残ではなく、日本語の美意識や伝統と深く関わっています。
俳句や和歌などの文学作品では、「羽」という表現が古くから使われてきました。
例えば、
月影に うさぎ一羽 ぴょんと跳ぶ
というように、詩的な表現では「羽」の方が風情を感じさせるため、今も用いられています。
一部の地域や方言では、昔ながらの言い回しとして「羽」を使うことがあります。
あまり一般的ではありませんが、呼び方には地域差が存在します。
文化・習慣として定着した理由
「羽」が今も残っている理由のひとつに、昔の人々の価値観や習慣が挙げられます。
ひとつに、「うさぎは鳥の仲間」と考えられていた名残が挙げられます。
平安時代や江戸時代には、「うさぎは鳥に近い存在」と見なされることがありました。
そのため、「羽」という数え方が定着したのです。
また、年配の方や伝統文化に関わる場面で「羽」が自然に使われることも。
特に昔の言葉を大切にする方々の間では、「羽」という表現が根付いている場合があります。
「匹」が主流になった現代でも、文化的・伝統的な背景から「羽」は一定の場面で生き続けています。
日本語は時代とともに変化します。
しかし、伝統的な表現が完全に消えることはなく、言葉の多様性として残っているのです。
うさぎの数え方の現状と正しい使い分け

現代では「匹」という数え方が圧倒的に主流となっています。
しかし先ほどもお話ししたように、「羽」という表現が完全に消えたわけではありません。
では、現在の日本語において「匹」と「羽」はどのように使い分けられているのでしょうか?
「匹」の使用が一般化している現状
最近の傾向を見ても、「うさぎ=匹」とするケースがほとんどです。
ペットショップ・動物病院では「匹」が標準的な表現となっています。
また、飼育書やSNSでも主流なのは「匹」です。
反対に、「羽」を使うケースは現在ではほとんどありません。
もちろん「羽」も間違いではありませんが、会話の中などで使う場合は「匹」の方が自然です。
「羽」が今でも使われる理由
一方で、「羽」という数え方が完全に消滅したわけではありません。
年配の方や、伝統文化に関心のある人々の間では今でも「羽」が使われることがあります。
また、一部の文学作品で使用されることも。
特に俳句や和歌などの詩的な表現では、今でも「羽」のほうが趣があるとされています。
今後は「匹」に統一されるのか?
今後の傾向として「匹」が主流になる可能性は高いですが、「羽」が完全に消えることはないと考えられます。
伝統的な表現として今後も文学作品や特定の場面で使われることが考えられます。
つまり、日常会話では「匹」、歴史的・文学的な文脈では「羽」といった使い分けが続いていくでしょう。
- 現在の日本語では「匹」が圧倒的に主流
- 一部の人の間では「羽」も使われ続ける可能性あり
ちなみに私は由来に少し抵抗があるので、「羽」という数え方はしていません。
このブログでも「匹」で統一しています。

ただし、どちらも決して間違いではありません
まとめ
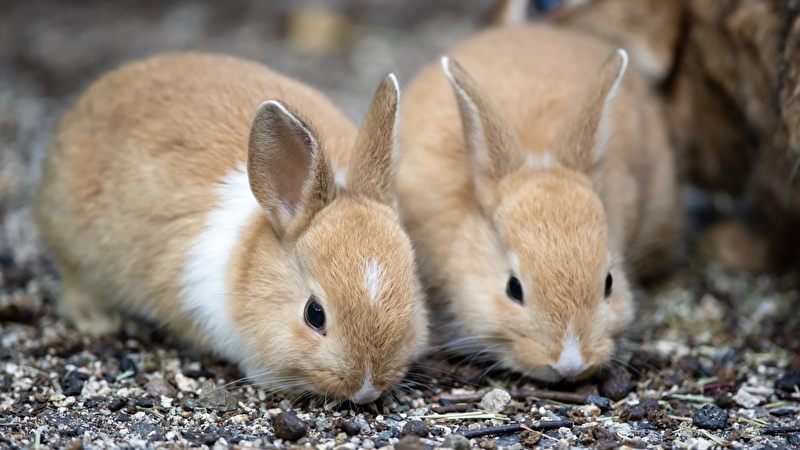
うさぎの数え方の由来はいくつも存在する
うさぎの数え方は、「匹」と「羽」が一般的です。
そのどちらも間違いではありません。
特に「羽」という数え方は、さまざまな理由から生まれました。
宗教的な背景や文化的な習慣、さらには見た目の特徴などが挙げられます。
現在では「匹」が主流となっていますが、伝統や文学の中では「羽」が使われることもあります。
言葉は時代とともに変化しますが、その背景を知ることで、より深く日本語の奥深さを感じられます。
うさぎの数え方を通じて、日本の歴史や文化に触れるきっかけになれば幸いです!